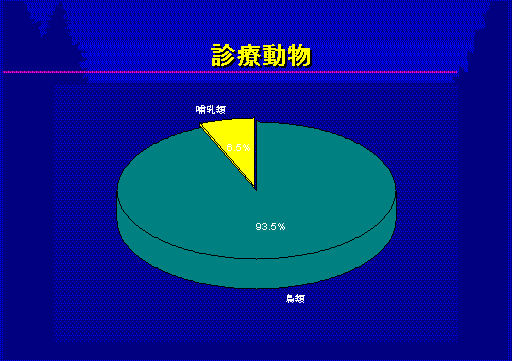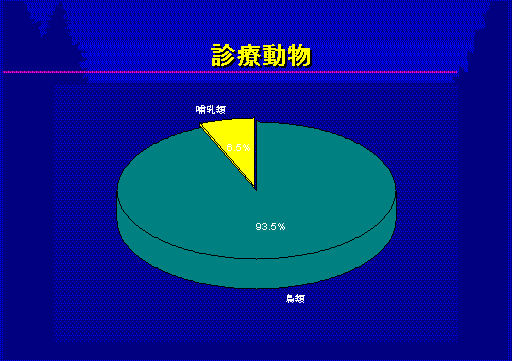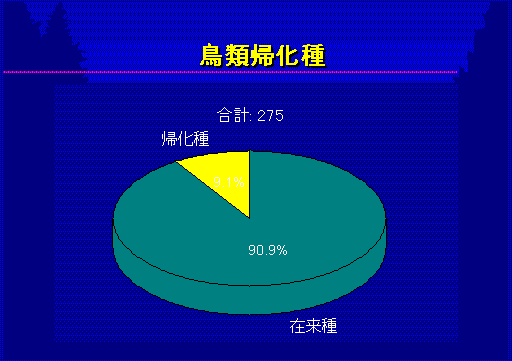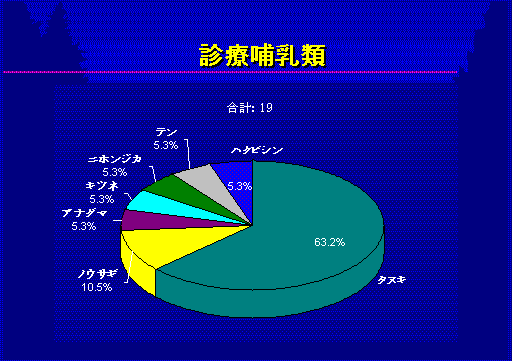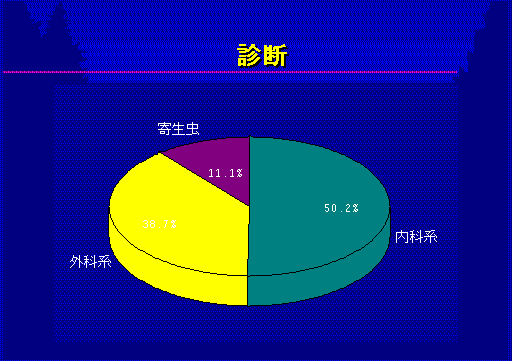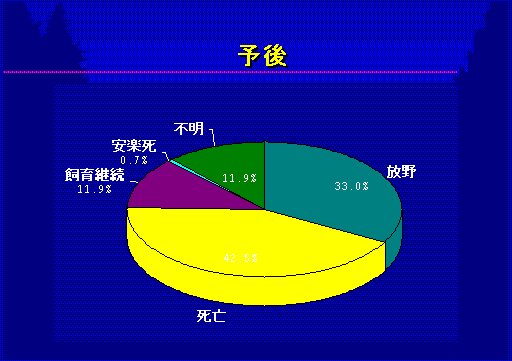野生動物救護獣医師協会診療集計報告
野生動物救護獣医師協会診療集計報告 その1 (1991)
佐々木泰造、○原修一、植松一良、馬場國敏、野口泰道(野生動物救護獣医師協会)
1、はじめに
1991年4月に環境指標としての傷病野生動物の診療とデーターの蓄積を目的として発足した野生動物救護獣医師協会の会員病院で診療を行った野生動物の症例についてカルテの集計を行ったので、その結果について報告する。
2、調査期間および方法
1991年4月から1992年3月までの1年間に野生動物救護獣医師協会所属の病院で保護加療を行った記録の内回収したカルテについて集計した。記録には同一の様式のカルテを用い、1年後に郵送により回収した。
3、結果
有効報告総数は294件、鳥類50種275件(93.6%)、哺乳類7種19件(6.4%)であった。
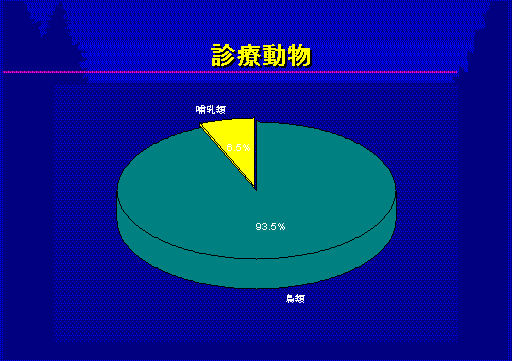
報告地域は、東京を中心とした1都3県で、東京都の多摩地区が最も多かった。
鳥類の内在来種は、47種250件(91.0%)、帰化種3種25件(8.9%)であった。
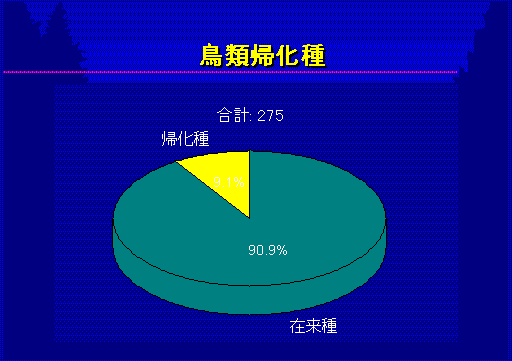
目別の報告数は、コウノトリ目14件(5.0%)、ガンカモ目28件(10.0%)、ワシタカ目8件(2.8%)、キジ目1件(0.5%)、チドリ目1件(0.5%)、ハト目62件(22.3%)、フクロウ目4件(2.2%)、キツツキ目2件(1.4%)、ブッポウソウ目3件(1.0%)、スズメ目152件(54.6%)であった。
哺乳類の内訳は、タヌキ12件(63.1%)、ノウサギ2件(10.5%)、アナグマ、キツネ、ニホンジカ、テン、1各1件(各5.2%)であった。
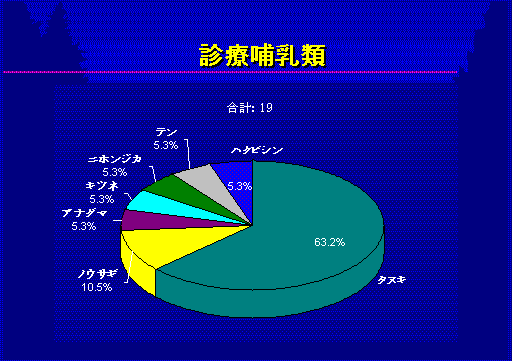
疾患別に分類すると、消化器障害を含む衰弱栄養障害が最も多く122件(38.4%)、ついで外傷が94件(29.7%)で、内部寄生虫27件(8.5%)、外部寄生虫7件(2.2%)の順であった。
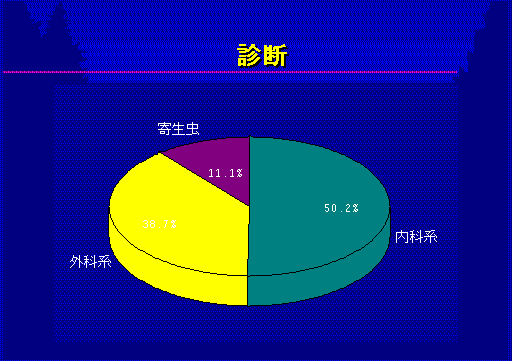
予後は、放野97件(32.9%)、死亡125件(42.5%)、飼育継続35件(12.0%)、安楽死2件(0.5%)、不明35件(12.0%)であった。
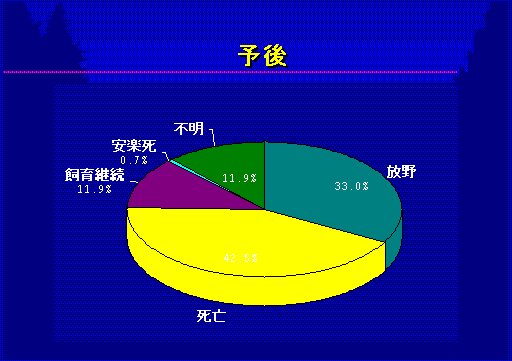
4、考察
会員病院数総診療件数と報告数の差は不明であるが、未回収が相当数あるものと推測された。記入集計が容易で継続的に実施できるカルテの必要性が示され、現在検討中である。
今回回答を寄せてくれた病院の立地は、都市郊外の住宅地がほとんどで、内陸の郊外住宅地における野生動物の疾病・傷害の発生状況、生息状況を反映していると思われた。
今回の調査で、都市近郊にも貴重な野生動物種が生息繁殖していること、交通事故等の外傷が多いことが示された。
今後も調査を継続し野生動物との共存の方法を検討する基礎データーを蓄積して行きたい。
5、協力病院
新ゆりがおか動物病院、鳥の病院、ダクタリ動物病院国立病院、ナガワ動物病院、大門動物病院、吉池動物病院、緑が丘動物病院、動物MEリサーチセンター、多摩総合動物病院、馬場動物病院、佐々木動物病院
平成8年度日本小動物獣医学会演題17
野生動物救護獣医師協会診療集計報告 その4 (1994)
1、はじめに
1994年1年間に、野生動物救護獣医師協会所属(WRV)の診療施設で加療を行った記録の内、回収したカルテについて集計した。
2、結果
有効報告総数は684件、10都道府県31施設よりカルテが回収された。動物別報告数は、鳥類634件(92.7%)、哺乳類49件(7.2%)、爬虫類1件(0.1%)であった。報告種数は、鳥類82種、哺乳類16種、爬虫類1種であった。報告全体の内外来種の占める割合は17.7%であった。
保護理由の内明確な記載のあったものは173件であり、その内訳は、交通事故47件(27.2%)、構造物に激突22件(12.7%)、人工施設(罠を含む)より救出13件(7.5%)、猫より救出63件(36.4%)、犬より救出4件(2.3%)、その他の動物より救出16件(9.2%)、誘拐8件(4.6%)であった。
臨床診断の系統的内訳は、環境系16件(2.3%)、外科系367件(53.7%)、内科系174件(25.4%)、神経系29件(4.2%)、寄生虫系17件(2.5%)、正常78件(11.4%)、不明3件(1.4%)であった。
予後の内訳は、放鳥獣214件(31.3%)、飼育継続120件(17.5%)、死亡289件(42.3%)、安楽死22件(3.2%)、不明39件(5.7%)であった。
3、考察
シマフクロウ (4羽)、タンチョウ (1羽)、シラコバト(2羽)、オオタカ
(4羽)、オオワシ(1羽)の6種12羽の稀少鳥類の症例が報告されており、稀少種の救命技術の確立が必要であると共に、死亡したケースにおける遺伝子の保存方法についても検討が必要であることが示唆された。
平成8年度日本小動物獣医学会演題18
野生動物救護獣医師協会診療集計報告 その5 (1995)
1、はじめに
1995年1年間に、野生動物救護獣医師協会所属(WRV)の診療施設で加療を行った記録の内、回収したカルテについて集計した。
2、結果
有効報告総数は968件、12都道府県36施設よりカルテが回収された。動物別報告数は、鳥類925件(95.6%)、哺乳類40件(4.1%)、爬虫類3件(0.3%)であった。報告種数は、鳥類82種、哺乳類11種、爬虫類3種であった。報告全体の内外来種の占める割合は15.9%であった。
保護理由の内明確な記載のあったものは214件であり、その内訳は、交通事故41件(19.2%)、構造物に激突34件(15.9%)、人工施設(罠を含む)より救出7件(3.3%)、猫より救出91件(42.5%)、犬より救出5件(2.3%)、その他の動物より救出20件(9.3%)、誘拐16件(7.6%)であった。
臨床診断の系統的内訳は、環境系32件(3.3%)、外科系479件(49.5%)、内科系228件(23.6%)、神経系45件(4.6%)、寄生虫系31件(3.2%)、正常150件(15.5%)、不明3件(0.3%)であった。
予後の内訳は、放鳥獣275件(28.4%)、飼育継続224 件 (23.6%)、死亡394件(40.7%)、安楽死25件(2.6%)、不明50件(5.2%)であった。
3、考察
加療動物のうち外来種の占める割合は15.9%を占め、特に爬虫類では全例とも外来種であった。
また哺乳類では、フェレットが4例保護されている。外来種の帰化は日本本来の生態系の破壊につながるばかりでなく、アライグマ回虫のような新たな人畜共通感染症や、日本から一度消失した狂犬病などの重篤な感染症をもたらす可能性が有り、対策の必要性が示唆される。
|REPORTS INDEX| WRVJ HOME|